「もしも」の前に備えることが、家族を守る力になる
「親の介護が始まりそう…」「最近、物忘れが増えてきたみたい」
そんな変化を感じたとき、頭をよぎるのが「認知症とお金の管理」ではないでしょうか。
💬 実は筆者も、母の認知機能に不安を感じ始めたころ、「成年後見制度」を知り、早めに調べておいて本当によかったと実感しました。
\あわせて読みたい/
👉【関連記事】親が病院を嫌がるときの声かけ実例7選|本人のプライドを守るコツ
成年後見制度って、どんなもの?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の
▶お金の管理
▶契約や手続きのサポート
をするために「代理人(後見人)」を立てる制度です。
2種類の制度があります
| 種類 | 使うタイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| 法定後見制度 | 認知症などで判断力が低下した後 | 家庭裁判所が後見人を決める |
| 任意後見制度 | 判断力があるうちに契約しておく | 自分で後見人を指定できる |
法定後見制度と任意後見制度のちがい
| 比較項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 利用のタイミング | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約 |
| 後見人の選び方 | 家庭裁判所が選任 | 本人が信頼できる人を指定 |
| 開始の手続き | 家庭裁判所に申立て、後見人選任後スタート | 契約後、将来必要になったら裁判所に申立て |
| メリット | すぐに使える制度 | 自分の意志で備えられる制度 |
成年後見人ができること・できないこと

✅ できること
・預貯金の管理 ・介護施設の契約
・年金や手当の手続き
⚠️ できないこと
・本人の住居売却(家庭裁判所の許可が必要)
・日常の些細な買い物(判断力が残っていれば本人の意思を優先)
利用するには?ざっくり流れを解説

【法定後見制度の場合】
- 家庭裁判所に申し立て(家族・専門職も可)
- 精神科医による診断書の提出
- 家庭裁判所が後見人を選任
- 後見人としての業務がスタート
⏰ 申立てから開始まで約2~3ヶ月ほどかかることが多いです。
【任意後見制度の場合】
- 元気なうちに信頼できる人と契約
- 公証役場で「任意後見契約」を結ぶ
- 将来、必要になったら家庭裁判所に申立て
- 後見監督人の選任→後見スタート
よくある疑問Q&A
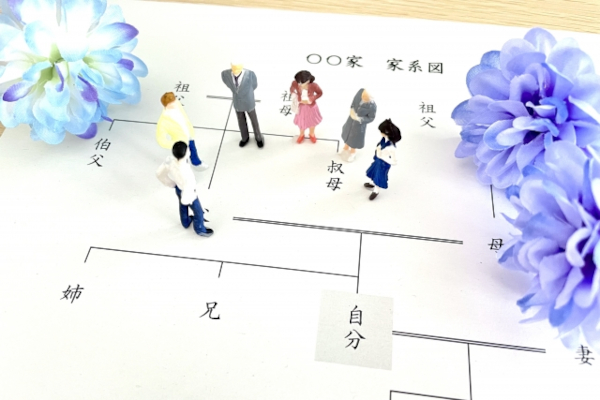
💭誰を後見人にすればいいの?
【答え】
家族でも、弁護士や司法書士などの専門職でもOKです。
信頼できるかどうかが一番大切です。
💭費用はかかるの?
【答え】
申立てに数万円~、専門職を立てる場合は月1~3万円が目安です。
▶地方自治体の【無料相談窓口】を活用すると安心です。
「まだ早いかも…」と思っているうちに困る人が多い

「まだ元気だから、後見制度なんて必要ない」と思っていると…
- いざ認知症が進行すると本人の意思確認ができず契約できない
- 銀行口座が凍結され、施設入所の費用が払えない
- 相続の手続きができず、トラブルになる
こんな状況に陥ってしまうケースも珍しくありません。
前向きに備える気持ちが、家族の安心につながる
制度を知ることは、「不安を取り除くための準備」です。
すぐに使わなくても、「こういう制度があるんだ」と知っておくだけで大きな安心につながります。

わたしも「まだ先」と思っていたけれど、知っていたおかげでスムーズに手続きできました。
親が笑って過ごせる時間を少しでも長くしたいですね。
まとめ|今日からできる小さな一歩

🔖この記事のポイント
・成年後見制度は、認知症などで判断力が低下した人を守る制度
・「法定後見」と「任意後見」がある
・早めに備えることで、家族の混乱を防げる
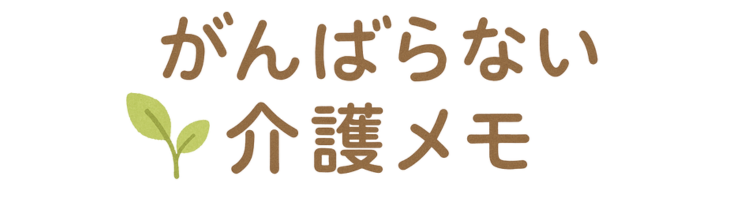



コメント