【この記事では】
在宅と施設、それぞれがどんな人に向くかと選び方のコツをわかりやすく解説します。
——本人の希望・家族の体力と時間・利用できる支援の3点を合わせて考えると、あなたの家庭に合う答えが見つかります。
在宅介護が向いているケース
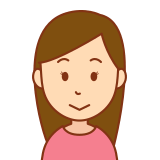
家が落ち着く。いつもの茶碗でごはんを食べたい——そんな“今まで通りの暮らし”を守れるのが在宅の強みですね。
在宅介護は自由度と安心感がある反面、家族の負担が偏りやすい面も。
地域包括支援センターに相談し、ヘルパー・通所・ショートステイを組み合わせて、ひとりで抱えない仕組みを作りましょう。
➡ 負担を軽くする工夫は【関連記事】親のトイレ介助がラクになる!自宅で使える介護補助アイテムまとめも参考になります。
施設介護が向いているケース

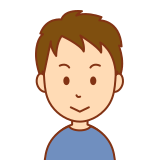
家族の時間と心を守るために、施設という選択肢を使う。それも立派な“自立支援”です。
施設にも種類があり、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・有料老人ホームなど、それぞれ役割が異なります。
➡ 特養と老健の違いはこちら
➡ 老人ホームの年齢と探し方のコツはこの記事をご覧ください。
迷ったときの考え方

- 本人の声を中心に
何が不安?何を続けたい?誰と過ごしたい?——できることを活かす環境を探します。 - 家族のリアルを見積もる
介護に使える時間・体力・距離は?夜間や入浴など負担が大きい場面は外部サービスを活用できるか確認します。 - 制度とサービスを最大活用
ケアマネに相談し、在宅+ショートステイや老健→在宅など段階的なプランも検討します。
よくある不安に寄り添うQ&A
Q1. 在宅介護は費用が安い?
A. 状況によります。介護サービスや福祉用具の費用はかかりますが、施設より日々の生活費が抑えられる場合も。月トータルで比較しましょう。
Q2. 施設に入ると会えなくなる?
A. 多くの施設で面会可能(時間・方法は施設による)。オンライン面会を取り入れる所も増えています。事前に“会える計画”を確認しましょう。
Q3. 途中で在宅↔施設に切り替えられる?
A. 可能です。介護状態や家族事情に合わせてケアプランを見直します。ショートステイで移行練習をするケースもあります。
Q4. 見学で何を見ればいい?
A. におい・表情・声かけの3つ。居室や浴室の清潔感、スタッフの接し方、食事の雰囲気も要チェック。
決め方のコツ

- 本人の希望(大切にしたい日課・友人関係・趣味)
- 家族の役割分担(平日・夜間・通院同行)
- 使える制度(介護保険・ショートステイ・福祉用具・住宅改修)
- 月額の目安(在宅・施設どちらも合計金額で)
- 3か月後の見直しポイント(続ける/変える判断基準)
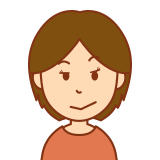
完璧を目指さず、7割の納得でスタート。3か月後に見直す——それが、がんばりすぎない介護のコツです。
まとめ

“本人の想い”と“家族の毎日”は同じくらい大切。
在宅にも施設にも、それぞれの良さとむずかしさがあります。だからこそ二択ではなく、組み合わせも視野に入れてみましょう。
今日できる一歩は、地域包括支援センターへ相談し、ケアマネとの面談を予約することです。そこから道がひらけます。
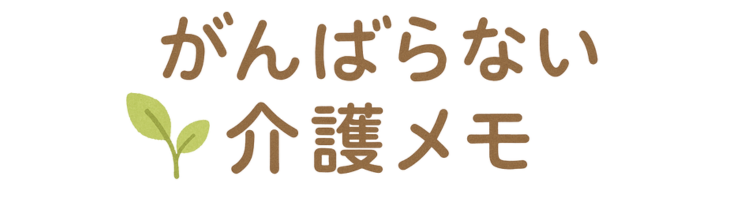



コメント