介護が始まると、想像以上にお金がかかるもの。でも、実は国や自治体からの「支援制度」をうまく使えば、負担をぐっと減らすことができます。
この記事では、介護に使える主なお金の制度と、申請のポイントをわかりやすく解説します。
「知らないまま自己負担してた…」なんてことにならないように、今のうちにしっかり知っておきましょう。
🏠介護保険サービスを使えば自己負担は1~3割に!
介護にかかるお金の多くは、「介護保険」を利用することでカバーできます。
対象は、65歳以上の方(または40歳以上で特定疾病がある方)。
介護サービスの費用は、原則1〜3割負担。
たとえば、10万円かかるサービスでも、1〜3万円で受けられることもあります。
ただし、サービスを受けるには「要介護認定」を受ける必要があります。
💰意外と知られていない!介護に使えるお金の制度

介護保険以外にも、実はたくさんの支援制度があります。
ここでは代表的なものを紹介します。
🔸1. 高額介護サービス費制度
介護サービスを使いすぎて自己負担が高額になった場合、上限を超えた分が払い戻される制度です。
たとえば、月に4万円払っていても、所得に応じて最大でも約4.4万円までに抑えられることも。
🔸2. 住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など、20万円までの工事に対して補助が出る制度です。
費用の1〜3割負担でリフォームできるので、在宅介護がグッと楽になります。
🔸3. 福祉用具のレンタル・購入補助
ベッドや車椅子など、福祉用具のレンタル費用の補助も受けられます。
レンタルの方が買うより安く済むケースも多いです。
「どんな福祉用具があるの?」という方は、
👉[介護をラクにするお助けアイテム特集はこちら]
🔸4. 医療費控除・介護費控除
介護の費用の中には、医療費控除の対象になるものがあります。
たとえば、医師の指導のもとで受けた訪問介護など。確定申告で戻ってくる可能性もあります。
🌸制度を使う前に知っておきたい3つのポイント

💡【1】「申請しないともらえない」が基本
ほとんどの制度は、申請しないと支給されません。
「知らなかった」で終わらせないように、早めに役所やケアマネージャーに相談を。
💡【2】「使える時期」や「上限額」が決まっている
住宅改修や給付金には上限があります。知らずに自己負担で進めてしまうと、あとから補助が受けられないことも。
💡【3】地域によって内容が違う
同じ制度でも、自治体ごとに金額や条件が少し違うことがあります。
詳細は、必ずお住まいの市区町村の介護課で確認を。
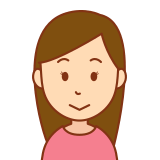
母の介護で、初めは全部自費でした。でも、ケアマネさんに教えてもらって申請したら、月に2万円以上も負担が減りました。
🌼よくある質問(FAQ)
Q1. どの制度を優先して使えばいいの?
A. まずは「介護保険」を優先し、そのうえで必要に応じて他の制度を組み合わせるのがおすすめです。
Q2. 申請は誰がすればいいの?
A. 基本は本人か家族ですが、ケアマネージャーが代行してくれることもあります。
Q3. どこで相談すればいい?
A. 市区町村の介護保険課、地域包括支援センター、またはケアマネージャーが窓口になります。
🌿まとめ|「知っているだけ」で介護の負担は変わる

介護は、体だけでなくお金の負担も大きいもの。
でも、支援制度をうまく活用すれば、家族の生活にも少し余裕が生まれます。
他にも、
👉[介護の負担を軽くする宅配サービスまとめ]もチェックしてみてくださいね。
🕊️さいごに
介護はがんばりすぎず、「使えるものは使う」ことが大切です。
制度を上手に活用して、少しでも心にゆとりを持てる介護ライフを目指しましょう。
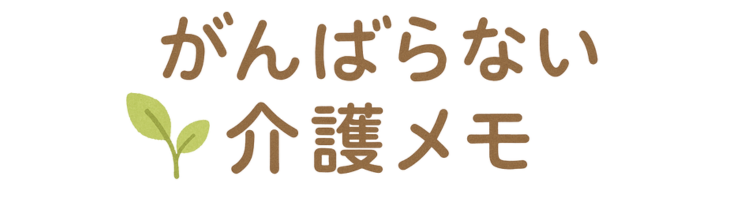
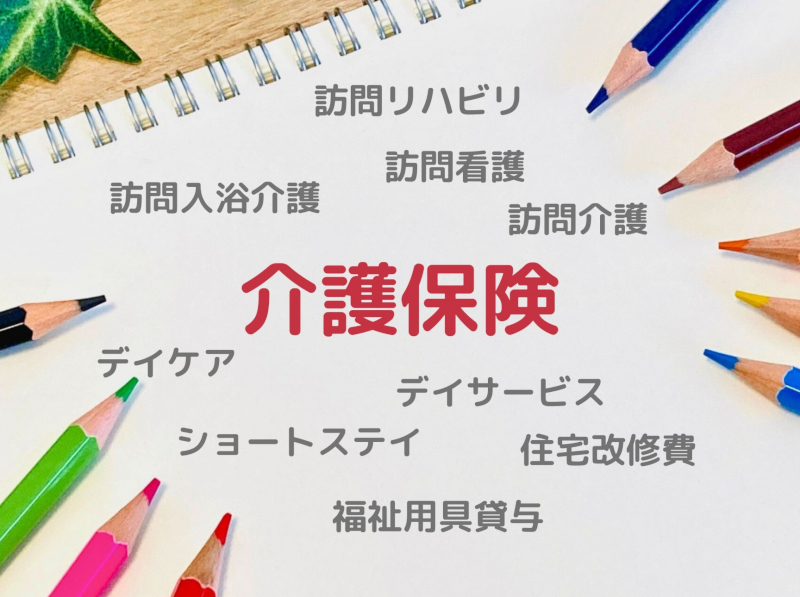


コメント